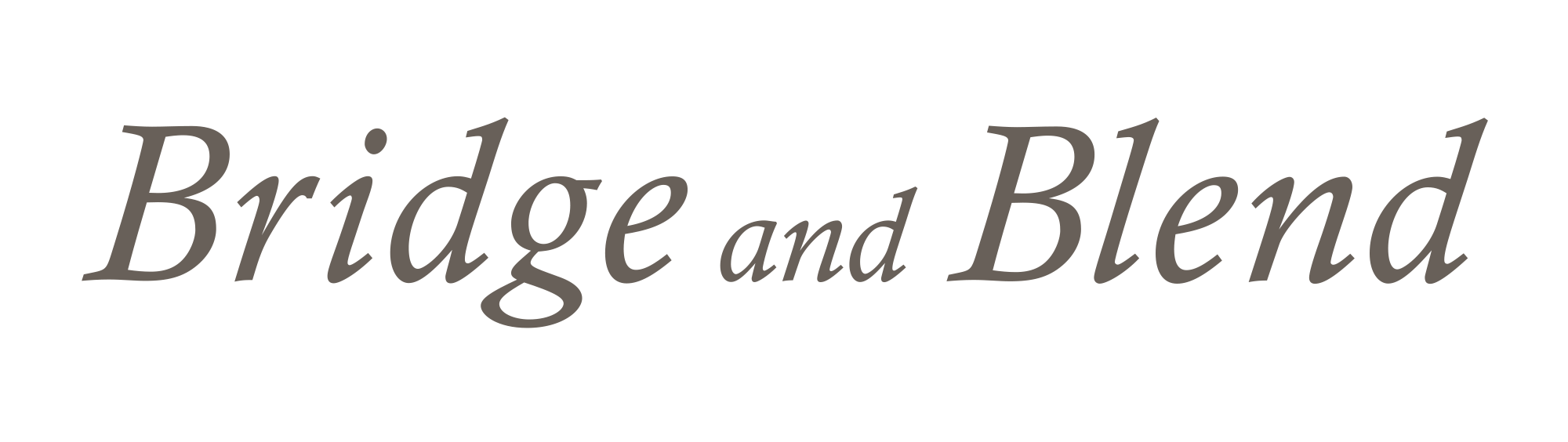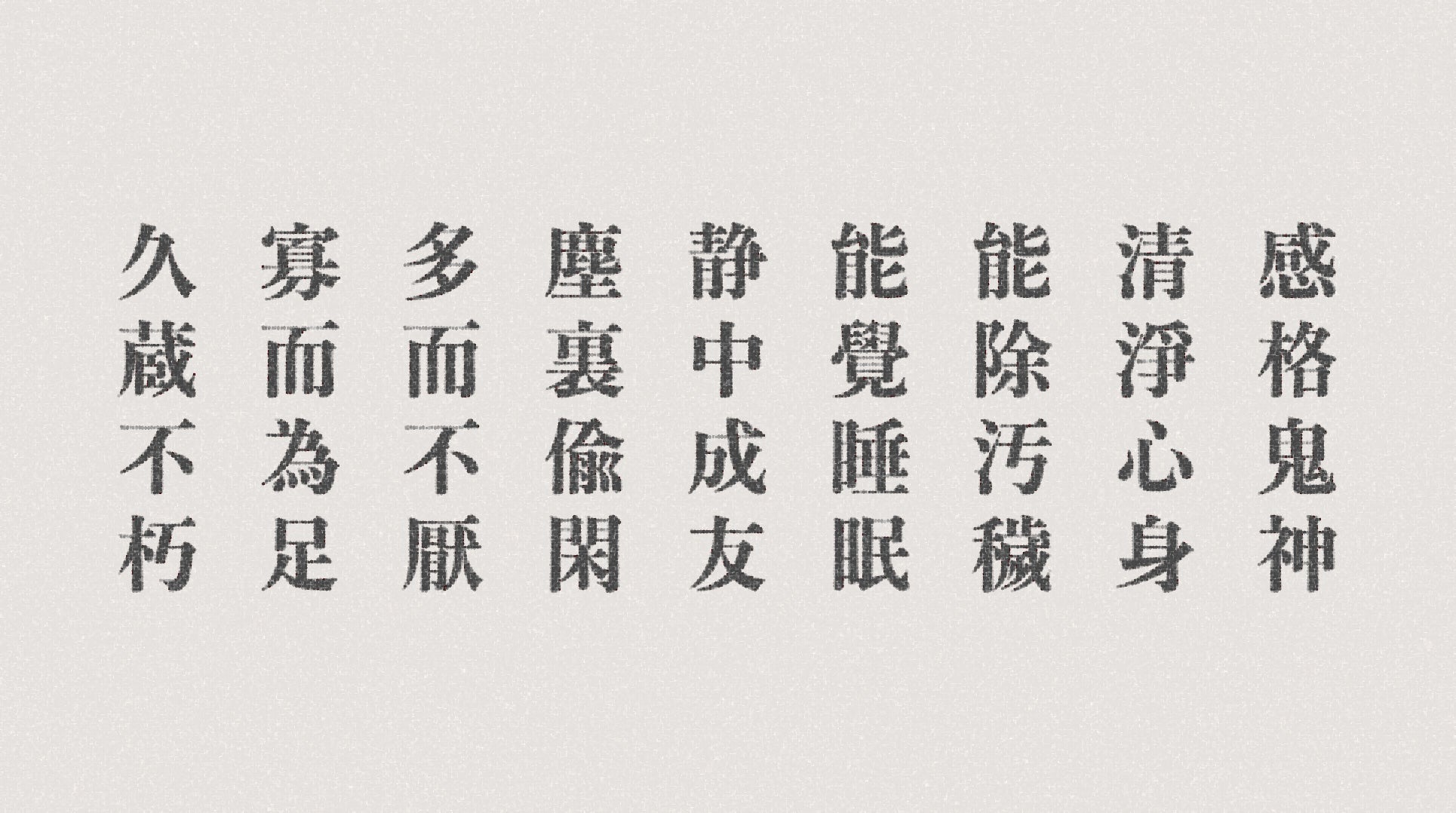Blog

いかがお過ごしですか? 「お香って作れるんですか?」とよく聞かれます。「作れます。料理をするのと同じです。」よくと答えます。(笑) Bridge and Blend が提供するワークショップは、源氏物語を体感するお香「Six in Sense」の中から一つの香りを創作体験するワークショップです。 2015 年より開催しており、シンガポール、ニューヨーク、東京、ロサンゼルスでの開催実績があり...
もっと見る
いかがお過ごしですか? 今回のお題「六種の薫物」。ついつい人に話したくなるお香の豆知識として知性と教養を披露できるかもしれません。 「六種の薫物」とは、平安時代に調香された 100 種類以上お香の中から、当時の人々の感性をよく表している 6 つの調香を指し、季節になぞらえた「梅花」「荷葉」「侍従」「菊花」「落葉」「黒方」となります。「六種の薫物」としてまとめられたのは、平安時代以降のよ...
もっと見る